さて本記事では予習シリーズ 6年上 実力完成問題集のレビューをさせて頂きます。
中学受験では定番である四谷大塚の予習シリーズです。
現在は新版が出ておりますが、旧版の実力完成問題集でも充分な学力が身に付けられるように思います。
メルカリ等で安価に手に入ると思います。
総復習用の問題集として 大変オススメ出来る問題集です。
四谷大塚 予習シリーズ6年上 実力完成問題集
表紙

目次

問題集概要
発行社 四谷大塚
224ページ(問題は4〜137ページ)
税込み 1760円
テーマ毎に18回分の問題が用意されている問題集。
5、9、14、18回はそれぞれ1〜4、6〜8、10〜13、15 〜17の総合復習問題。
よってテーマ数としては14テーマ。
テーマ1回につき
- 反復基本問題 4題
- 反復練習問題 6題
- 基本問題 3題
- 練習問題 6題
- 応用問題 3題
以上で 合計 22題/テーマ
程度が掲載されています。
テーマのうち【総合回】については
- 基本問題 5題
- 練習問題 5題
- 応用問題 4題
以上で 合計 14題/総合会1回
程度の問題が掲載されています。
これらを合わせた掲載されている問題数は
大問数で約364題 です。
中堅~難関中学の過去問中心の問題集です。
難易度
全ての問題が公立小学校の問題と比べて、非常に難易度が高い。
一般的な公立小学校の6年生は手も足も出ないレベル感です。
四谷大塚の【6年】というのはあくまで 6年生まで中学受験塾で学んできたお子様 という意味合いです。
難易度は問題によって異なりますからあくまで目安である事を御承知おき下さい。
反復問題
- トップクラス問題集4年のハイクラスA~Bと同レベル
- 自由自在問題集の標準と同レベル
- プラスワン問題集と同レベル
- 予習シリーズ5年上下 基本問題と同レベル
基本問題
- トップクラス問題集4年のハイクラスA~Bレベル
- 自由自在問題集の標準と同レベル
- プラスワン問題集と同レベル
- 予習シリーズ5年上下 基本問題と同じ
練習問題
- トップクラス問題集4年のトップクラスと同じかやや難しい
- 自由自在問題集の発展と同レベルかやや難しい
- プラスワン問題集よりやや難しい
- 予習シリーズ5年上下 応用A と同レベル
応用問題
- トップクラス問題集4年のトップクラスより難しい
- 自由自在問題集の発展と同レベルかより難しい
- プラスワン問題集より難しい
- 予習シリーズ5年上下 応用A~B と同じ
良い点
- 解答が丁寧で非常に分かりやすく子供が一人でも学びやすい。
- 予習シリーズ本編を買わなくても良質な問題集として機能する。
- 近年の出題傾向に合わせてまとめられており受験対策用の教材として優れている。
- 問題数が多く、非常に網羅性が高い。6年生の総復習に最適。
- クオリティとボリュームの割に1760円と安価
メルカリ等で買えば300円~
※総復習にはプラスワン問題集より 本問題集の方が個人的にはオススメです。
悪い点
- 解答が一体型です。別冊なら尚良かった。
- 難問は少ないので、難関~最難関には対応出来ない
正直なところ悪いところがあまり見つからない素晴らしい 総復習用の問題集 だと思います。
市販の 総復習用問題集の中では これが最も良いと思えるレベルです。
出題範囲と網羅性
- 四谷大塚で6年上期までに習う範囲全て。
- 本問題集まで終われば、中学受験範囲は全て網羅されます。
※一部ヌケがありますが、問題無いレベルだと思います。 - 中堅中学までならば本問題集を完璧にする事で高得点が狙える。
- 地方の中学受験では本問題集は完全にオーバースペックです。
推奨時期
予習シリーズ5年下の応用演習問題が終わった後
自由自在問題集の発展まで学習した後。
我が家の場合は以下のように進めました。
- 教科書ぴったりトレーニング中学3年まで
- トップクラス問題集4年
- 自由自在問題集
- 予習シリーズ5年上 最難関問題集
- 予習シリーズ5年下 応用演習問題集
- 本問題集
というルートです。
学習ルートの詳細はこちらの記事を御参照下さい。

進め方(参考)
愚直に第1回から順番に全ての問題を解きました。
2周目も全問題を解きました。
3周目は間違えた問題のみ解きました。
4周目以降は間違えた問題のみを解き、全問正解するまで反復しました。
算数、数学は演習量が大事です。
とにかく演習を積み、問題の解き方、条件整理の仕方を身に付けます。
大量演習をしているうちに解法を暗記していきます。
そして、何となく解けるルートが見えるようになります。
数学の学習と同じですね。
予備校の先生の授業を聞いたら大学二次試験が解けるようになるかと言えばなりません。
自分で手を動かして、解答に辿り着いた経験が必要です。
関連記事


我が家の学習事例が少しでも家庭学習に取組む皆様の御参考になりましたら望外の喜びです。
ではまた!







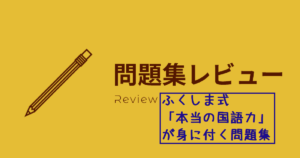


コメント【コメント非公開、メールでの返信を御希望される方はその旨をご記入下さい】